
本記事では、遺品整理を自分で行う方法と必要な準備について詳しく解説していきます。
自分で遺品整理を進めていく場合の注意点なども解説し、役立つ内容になっていますのでぜひ参考にしてください。
クリーンメイトでは、遺品整理士資格だけでなく、都道府県知事許可 塗装工事業、内装仕上工事業の許可など様々な資格を保有しておりますので、安心してお任せください。
もくじ
遺品整理を自分で行う方法は?必要な準備を詳しく解説

本記事では、遺品整理を自分で行う方法と必要な準備について詳しく解説していきます。 自分
で遺品整理を進めていく場合の注意点なども解説し、役立つ内容になっていますのでぜひ参考
にしてください。
遺品整理を自分で行う理由

遺品整理の重要性とは
遺品整理は、亡くなった方の持ち物を片付けるだけでなく、遺族の心の整理や、これからの生活のためにとても大切な作業です。
①心の整理に繋がる
故人の思い出に触れながら、心の整理をする大切な機会でもあり、遺品を通じて家族の記憶やつながりを再確認できる時間になります。
②大切な書類や財産を見つけるため
通帳や保険、遺言書など、重要なものを発見できることがあります。
③空き家や不動産の手続きに必要
空き家を売却・賃貸・解体するにはまず整理が必要であり、家財の整理・撤去を怠ると資産が負債になる可能性もあります。
④残された家族の負担軽減につながる
整理を先延ばしにすると体力的にも精神的にも大きな負担になることがあり、プロの業者に依頼することで親族間のトラブル防止にもなるでしょう。
⑤生前整理や終活を考えるきっかけになる
遺品整理を通じて「自分の老後」について考える人も多く、自分の将来を考えるよいタイミングにもなります。
自分で行うメリットとデメリット
遺品整理を自分で行う際のメリットとして、まず、費用を大幅に抑えられる点が挙げられます。
また、自分のペースで進められるため、時間をかけてじっくりと整理することが可能です。
しかし、デメリットとして、体力的に無理がある場合や、感情的に辛い作業であることが考えられます。
特に、一人暮らしの故人の遺品整理では、引き取る物の判断が難しいこともありますので、事前にしっかりと検討した上で行うことが重要です。
遺品整理を行うための準備

作業を始める前に確認しておくこと
遺品整理を始める前には、作業の範囲を明確にし、どの部屋やエリアを整理するかを確認しておく必要があります。
加えて、近隣の住人への配慮も重要ですので、音やゴミの処理に関して注意を払うようにしましょう。
また、もし必要な許可がある場合は、事前に取得しておくことで、スムーズに作業を進めることができるでしょう。
必要な道具と役割、物品リスト
遺品整理を自分で行う場合は、作業を安全かつスムーズに進めるために道具の準備がとても大切です。まず必要なのは、ゴミ袋です。
大量の不用品が出るため、破れにくくて大きめの袋を多めに用意しましょう。自治体の分別ルールに合わせて、可燃・不燃・資源ごとに使い分けられると便利です。
思い出の品や大切な書類を保管しておくためには、段ボールや収納ケースが役立ちます。中
身がわかるようにマジックペンや付箋でラベルを貼っておくと、後で探す手間が省けます。
そのほかにも、カッターやガムテープ、メモ帳、はさみなどの道具も必要です。
掃除も同時に進めるなら、雑巾や掃除機、ブルーシートもあると便利です。家具や大量のゴミを処分場に運ぶ場合は、軽トラックなどの車両も考えておくとよいでしょう。
服装は、動きやすくて汚れてもいいものを選びましょう。
このように、事前に道具をそろえておくことで、無駄な時間やトラブルを減らし、落ち着いて作業を進めることができます。
遺品整理の仕分けと整理方法

大切なものと不用品の見極め
遺品整理では、まず大切なものと不用品を見極めることが重要です。具体的には、思い出や価値を持つ品物を優先的に残し、それ以外は不用品として処分を検討しましょう。
判断に迷う場合は、家族と話し合うことが有効です。
また、ゴミ屋敷にならないよう、定期的に仕分けを行い、運搬や廃棄の計画も立てておくと良いでしょう。
不用品処分の具体的な手順
遺品整理では、思い出の品や必要なものだけでなく、多くの不用品も出てきます。これらを適切に処分するには、まず仕分け作業から始めましょう。
まず最初に行うのは、「残すもの」と「処分するもの」の分類です。アルバムや手紙、形見として家族に渡す品、大切な書類や貴重品は残します。
一方、壊れていたり明らかに使わないものは処分対象になります。
次に、処分するものをさらに分別していきます。
家庭ごみとして捨てられるもの(紙くずや衣類など)と、粗大ごみやリサイクル対象になるもの(家具、家電、金属類など)に分けていきます。
分別が終わったら、処分方法を確認します。可燃・不燃ごみなど通常の家庭ごみは、地域のルールに従ってごみ収集日に出します。
粗大ごみについては、自治体への申し込みが必要な場合が多く、事前に回収日や手数料の確認をしておきましょう。
まだ使える家具や家電がある場合は、リサイクルショップへの持ち込みや出張買取を利用する方法もあります。
また、処分に困る家電(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど)は「家電リサイクル法」の対象となるため、指定された方法で処分する必要があります。
分別や搬出に時間がかかる、体力的に難しいという場合は、不用品回収業者や遺品整理の専
門業者に依頼するのも一つの手です。見積もりを取って、安心できる業者を選ぶことがポイントです。
遺品整理に伴う注意点
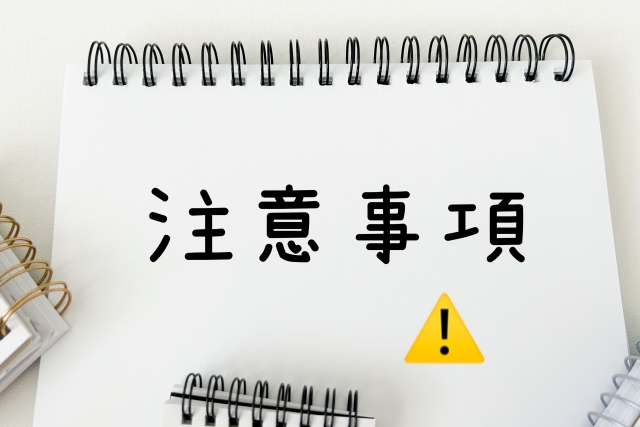
よくある問題とその対策
①トラブルを事前に把握する
②整理の計画を立てる
③専門家に相談する
遺品整理を自分で行う際には、よくあるトラブルを理解し、それに対する対策を講じることが重
要です。たとえば、整理中に発生する可能性のあるトラブルを事前にリストアップし、計画を立てておくことで、スムーズに作業を進めることができます。また、必要に応じて専門家の助けを借りるのも良い方法です。自分だけで解決しようとせず、困った時は頼ることも選択肢に入れましょう。
感情的にならないための心構え
①冷静に進めるためのルールを決める
②思い出に浸らない時間を設ける
③必要なものだけを選別する
遺品整理は感情的になることが多いため、冷静に進めるためのルールを決めておくことが大切です。
特に、思い出の品を前にすると感情が高ぶりやすいですが、思い出に浸らない時間を設けて冷静さを保つことが求められます。
また、無理にすべてを残そうとせず、必要なものだけを選別することで、心の負担を軽減できます。
無理のないペースで行うことが心の健康にもつながります。
遺品整理のことはクリーンメイトにおまかせください!
本記事では、遺品整理を自分で行うために必要な準備に焦点を当てて解説しました。
遺品整理の目的として、故人の思い出を振り返りながら心の整理を行い、大切な書類や財産の発見、不動産手続きの準備、家族の負担軽減にもつながることでしょう。
また、準備と進め方のポイントとしては、作業範囲の確認、近隣への配慮、必要な道具(ゴミ袋、段ボール、掃除用品など)を事前に用意し、分別・処分方法も自治体ルールに沿って進めることが重要です。
また、感情とトラブルへの対処法として挙げられるのは、思い出に浸りすぎないようルールを設け、判断に迷ったら家族と相談。
無理せず必要に応じて専門業者に依頼するのも一つの手ということです。
現在、悩まれている方にとって本記事の内容がお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
■関連HP
特殊清掃(クリーンメイト特殊清掃専門HP)についての詳しい内容はこちらもご覧ください。

クリーンメイトは3,000件以上の実績を誇りながらも、やり直し・クレーム等は現在まで一度もありません。
作業にあたるスタッフは、経験豊富で正しい知識を持つスタッフが担当します。
【対応エリア】
関西エリア(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀)、東海中部エリア(愛知・岐阜・三重・静岡・新潟・富山・石川・福井・長野・山梨)、関東エリア(東京・千葉・埼玉・神奈川・群馬・栃木・茨城)、北海道東北エリア(北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)中国四国エリア(鳥取・島根・岡山・広島・香川・愛媛・徳島・高知)、九州沖縄エリア(山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)一円
遺品整理、生前整理、特殊清掃およびリサイクル品買取、ゴミ屋敷片付け、法人向けサービスなども行っています。
大阪・関西エリアのほか日本全国対応可能です。
私たちクリーンメイトでは、長年の経験から遺品整理・家財整理に関する知識を持ち、遺品整理士協会から認定をいただいている企業ですので、お悩みの方は一度ご相談ください。
また、家財買取も行っておりますので、ご希望の方はお見積り時に担当までお声掛けください。
24時間年中無休対応(相談・お見積り無料)となっており、お電話以外にも、問い合わせフォーム(メール)やLINEからも可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

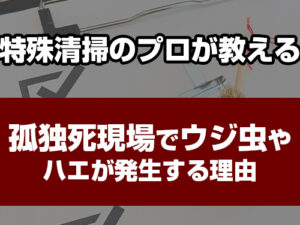
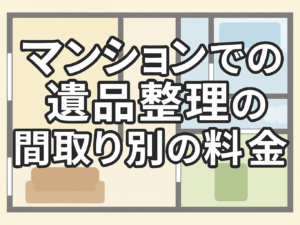
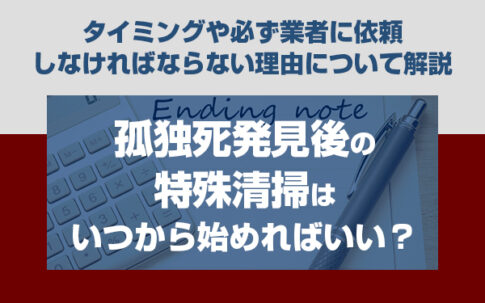
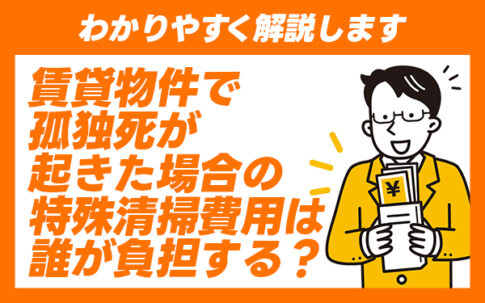
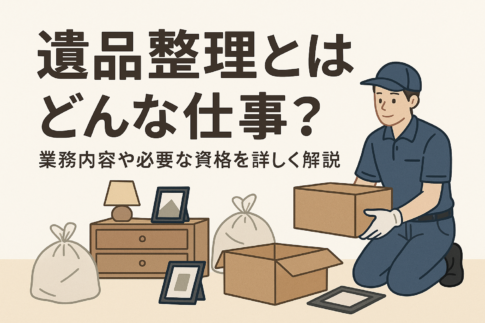

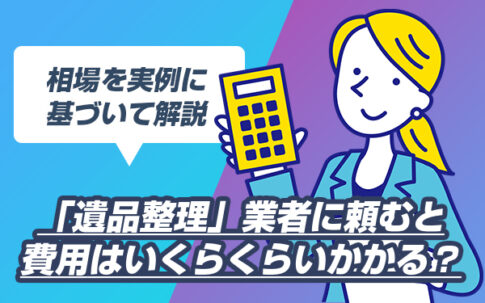

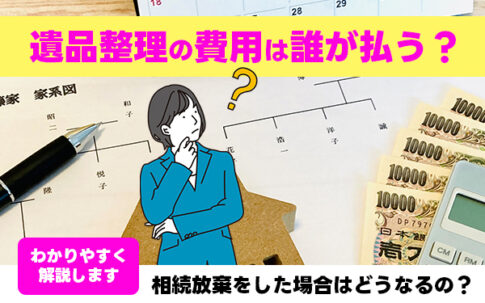
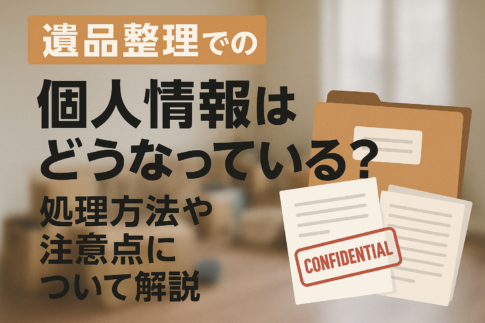
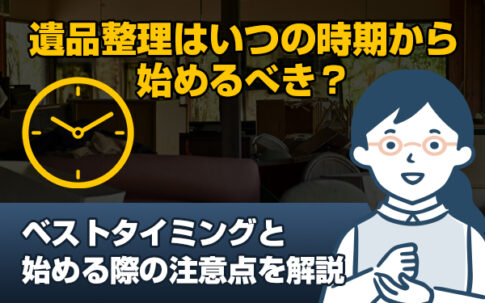


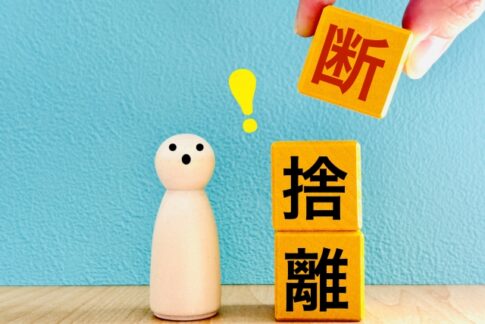




①事前に作業の範囲を確認
②周囲への配慮を忘れずに
③必要な許可を取得する